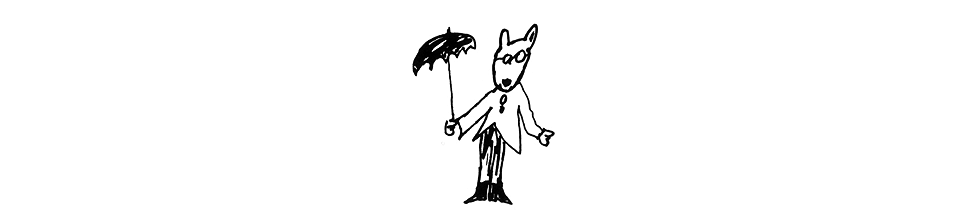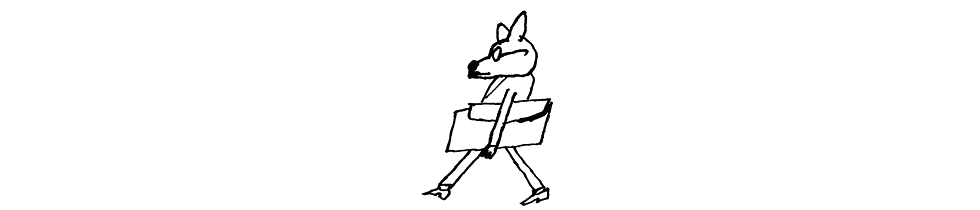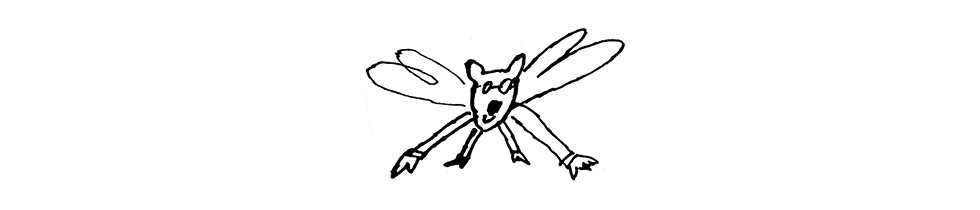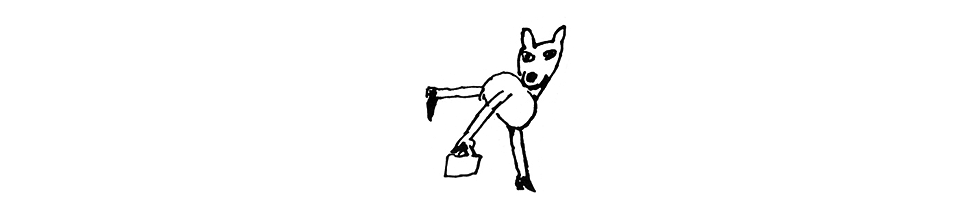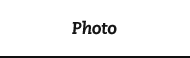今年も円安が続いた。数日前に日銀が0.25%の利上げを発表したが円安を続いている。利上げをめぐっては大騒ぎをしているけども、他の主要経済とくらべても日本の実質金利の低さは際立っている。
先日、経団連が主催した経済セミナーで、高市政権の経済ブレーンと言われている3名のエコノミストのプレゼンとパネルディスカッションを聴く機会があった。2時間ほどの時間のなかで為替に関する議論はほとんどされなかった。「責任ある積極財政」がいかに正当なものであるかという話ばかり。ステージ上の3名は所属する組織は違えど、「同じ穴のムジナ」と言っては失礼だが、現政権の経済政策のアドバイザーと言われている人たちだ。
彼らから為替の話がほとんどなかったことはどう理解すればいいのか?彼らは世の中で一定の評価がある人たちであり、経済政策が国内だけで完結しているわけではなく、国際経済の中で日本経済があること、円安がいまの物価高の最大要因のひとつであることをよくわかっている人たちだ。そして現政権にとって物価高対策は優先事項の一つのはずだ。
いまのような状況が続く限り、来年以降も円安は続くだろう。円安が加速し、止められなくなるかもしれない。あるいはヘッジファンドがさらに円安を加速させるような動きを強めることで一ドル200円というような水準にさえ近づくことが来年はあるのかもしれない。
日本経済の停滞はもう30年になろうとしている。これまでさんざん財政政策、金融政策を繰り出してみても、根本的な経済の改善にはつながっていない。日本株が4万円、5万円と上がってきたのは、政府の経済政策のおかげではなく、個別企業の努力であったり、いわゆるコーポレート・ガバナンスや東証の改革の成果によるのではないかと思うのだが、どうだろうか。
アベノミクスからはじまりいまの高市政権の経済政策を好意的に見ている人たちも、海外旅行に行くだろう。海外の物価が日本とは比較にならないほど高く、円が現地通貨に対して悲しいほど弱いことを体験してどう考えるのだろうか。アベノミクスがいまのような円安を招いた原因だとは考えないのだろうか。
ぼくが初めてアメリカの高校に留学した1976年は一ドルあたり290円から300円前後。その次にアメリカに留学した1985年から1987年は240円前後から145円前後と、プラザ合意を経て大きく円高に動いた時期だった。
最高値だったときには一ドル78円前後まで上がった円の価値はいまその半分になった。
来年も引き続き円安がつづくのだろうか。